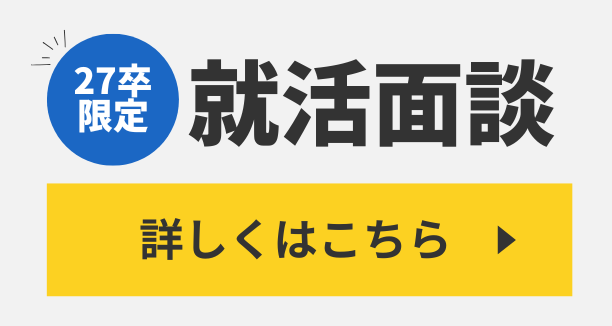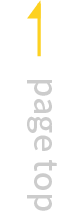このような自然科学の知は、「自分」を環境から切り離して得たものであるから、誰に対しても普遍的に通用する点で、大きい強みを持っている。自然科学の知はどこでも通用する。しかし、ここで一旦切り離した自分を、全体のなかに入れ、自分という存在とのかかわりで考えてみるとどうなるか。なぜ、自分はこのような太陽の運行と関連する地球に住んでいるのか。自分は何のために生きているのか、などと考えはじめるとき、自然科学の知は役に立たない。それは出発の最初から、自分を抜きにして得たものなのだから、当然のことである。太陽の動きや、はたらきは、自分と無関係に説明できる。しかし、他ならぬ自分という存在と、太陽とは、どうかかわるか。
太陽と自分とのかかわりについて、確たる知を持って生きている人たちについて、ユングは彼の自伝のなかで述べている。ユングが旅をしてプエブロ・インディアンを訪ねて行ったときのことである。インディアンたちは、彼らの宗教的儀式や祈りによって、太陽が天空を運行するのを助けていると言うのである。「われわれは世界の屋根に住んでいる人間なのだ。われわれは太陽の息子たち。そしてわれらの宗教によって、われわれは毎日、われらの父が天空を横切る手伝いをしている。それはわれわれのためばかりでなく、全世界のためなんだ」とインディアンの一人は語った。彼らは全世界のため太陽の息子としての勤めを果たしていると確信している。これに対して、ユングは次のように『自伝』の中で述べている。
「そのとき、私は一人一人のインディアンにみられる、静かなたたずまいと『気品』のようなものがなにに由来するのかが分かった。それは太陽の息子ということから生じてくる。彼の生活が宇宙論的意味を帯びているのは、彼が父なる太陽の、つまり生命全体の保護者の、日毎の出没を助けているからである」
インディアンたちは彼らの「神話の知」を生きることによって、ユングが羨望を禁じ得ない「気品」をもって生きている。これに対して、近代人は何とせかせかと生きていることか。近代人は豊かな科学の知と、極めて貧困な精神とをもって生きている。
(出典:河合隼雄『イメージの心理学』)
【設問】
文章の内容と一致するものを、次のA~Eの中から1つ選べ。
例題:
A. 現代人にとって自然科学の知は、人によって異なる、扱いにくいものである
B. 自分が生きる意義を考えるとき、自然科学の知は役に立たない
C. インディアンは、自然と自分との関わりという概念を持っていない
D. 現代人は、自分たちを太陽の息子たちととらえて生きている
E. 現代人がせかせかと生きている原因は、宇宙論的意味を得ているからである
自然科学をとらえる際、人間は自身の存在を切り離して観察するため、自然や世界、命の問題と自分自身との関わりを持てなくなっているから。
このような自然科学の知は、「自分」を環境から切り離して得たものであるから、誰に対しても普遍的に通用する点で、大きい強みを持っている。自然科学の知はどこでも通用する。しかし、ここで一旦切り離した自分を、全体のなかに入れ、自分という存在とのかかわりで考えてみるとどうなるか。なぜ、自分はこのような太陽の運行と関連する地球に住んでいるのか。自分は何のために生きているのか、などと考えはじめるとき、自然科学の知は役に立たない。それは出発の最初から、自分を抜きにして得たものなのだから、当然のことである。太陽の動きや、はたらきは、自分と無関係に説明できる。しかし、他ならぬ自分という存在と、太陽とは、どうかかわるか。
太陽と自分とのかかわりについて、(イ)確たる知を持って生きている人たちについて、ユングは彼の自伝のなかで述べている。ユングが旅をしてプエブロ・インディアンを訪ねて行ったときのことである。インディアンたちは、彼らの宗教的儀式や祈りによって、太陽が天空を運行するのを助けていると言うのである。「われわれは世界の屋根に住んでいる人間なのだ。われわれは太陽の息子たち。そしてわれらの宗教によって、われわれは毎日、われらの父が天空を横切る手伝いをしている。それはわれわれのためばかりでなく、全世界のためなんだ」とインディアンの一人は語った。彼らは全世界のため太陽の息子としての勤めを果たしていると確信している。これに対して、ユングは次のように『自伝』の中で述べている。
「そのとき、私は一人一人のインディアンにみられる、静かなたたずまいと『気品』のようなものがなにに由来するのかが分かった。それは太陽の息子ということから生じてくる。彼の生活が宇宙論的意味を帯びているのは、彼が父なる太陽の、つまり生命全体の保護者の、日毎の出没を助けているからである」
インディアンたちは彼らの「神話の知」を生きることによって、ユングが羨望を禁じ得ない「気品」をもって生きている。これに対して、近代人は何とせかせかと生きていることか。近代人は豊かな科学の知と、極めて貧困な精神とをもって生きている。
(出典:河合隼雄『イメージの心理学』)
【設問】
(イ)「確たる知」の説明について最も適したものを次のA~Eの中から1つ選べ。
例題:
A. 太陽が天空を運行しているということ
B. 太陽の動きや働きを、自分と無関係に説明できること
C. 自分たちが世界の屋根に住む人間だと自覚していること
D. 全世界のため、太陽の息子としての勤めを果たしていること
E. 自分たちが静かなたたずまいと気品を持っているということ
確たる知は、本人たちの中で確信を持ったものである。それがDの内容である。
このような自然科学の知は、「自分」を環境から切り離して得たものであるから、誰に対しても普遍的に通用する点で、大きい強みを持っている。自然科学の知はどこでも通用する。しかし、ここで一旦切り離した自分を、全体のなかに入れ、自分という存在とのかかわりで考えてみるとどうなるか。なぜ、自分はこのような太陽の運行と関連する地球に住んでいるのか。自分は何のために生きているのか、などと考えはじめるとき、自然科学の知は役に立たない。それは出発の最初から、自分を抜きにして得たものなのだから、当然のことである。太陽の動きや、はたらきは、自分と無関係に説明できる。しかし、他ならぬ自分という存在と、太陽とは、どうかかわるか。
太陽と自分とのかかわりについて、確たる知を持って生きている人たちについて、ユングは彼の自伝のなかで述べている。ユングが旅をしてプエブロ・インディアンを訪ねて行ったときのことである。インディアンたちは、彼らの宗教的儀式や祈りによって、太陽が天空を運行するのを助けていると言うのである。「われわれは世界の屋根に住んでいる人間なのだ。われわれは太陽の息子たち。そしてわれらの宗教によって、われわれは毎日、われらの父が天空を横切る手伝いをしている。それはわれわれのためばかりでなく、全世界のためなんだ」とインディアンの一人は語った。彼らは全世界のため太陽の息子としての勤めを果たしていると確信している。これに対して、ユングは次のように『自伝』の中で述べている。
「そのとき、私は一人一人のインディアンにみられる、静かなたたずまいと『気品』のようなものがなにに由来するのかが分かった。それは太陽の息子ということから生じてくる。彼の生活が宇宙論的意味を帯びているのは、彼が父なる太陽の、つまり生命全体の保護者の、日毎の出没を助けているからである」
インディアンたちは彼らの「神話の知」を生きることによって、ユングが羨望を禁じ得ない「気品」をもって生きている。これに対して、近代人は何とせかせかと生きていることか。近代人は豊かな科学の知と、極めて貧困な精神とをもって生きている。
(出典:河合隼雄『イメージの心理学』)
【設問】
文中の( ① )に当てはまる言葉を、次のA~Eの中から1つ選べ。
例題:
A. 経験
B. 技術
C. 知識
D. 能力
E. 情報
「自然科学の知」についての言及であるから、最終目標は知である。
死に勝る苦しみ、という表現がある。では死は苦しみの極限としてあるのか。そうではあるまい。苦しむのは生である。苦しみは生きていることの一つの証である。生の状態である。死が生の終わりなら、死は苦しみの終わりでもある。しかし、繰り返すが、私という第一人称にとって、死は、完璧な未知である。本当に死は苦しみの終わりなのかどうか、それを言うことさえ不可能なものとして、死はある。
したがって、いわゆる死への恐怖は、苦しむ生への恐怖を含んでいるにせよ、それだけではあるまい。
生への盲目的な執着が、ヒトが生物であることの明証であるとすれば、死への恐怖はヒトが人間であることの明証であると言えぬだろうか。
第三人称の死は、私にとって、消滅であり、消失であった。したがって、それは、本当の意味での「死」ではない。自分の前に立ちはだかる未知の深淵としての死の何たるかを知ろうとする、空虚(むな)しい努力のための、何らの糧にもならない。自分の万年筆やハンカチや財布をいくら紛失したとしても、それで自分の死について何か感ずるところがあったとは言えまい。
そして、第一人称の死、つねに未来形でしかありえないものが、現実化したとき、「私」は誰からも手助けを受けることなく、完全な孤絶のなかで、それを体験することになる。第三人称の死が、「私」とって消滅であるならば、第三者にとって「私」の死は同じように単なる消滅以外のものではありえないだろう。「私」にとって一度も体験したことのない「私の死」を、私は、自分以外の一切の他に対して架すべき何らかの橋堡(きょうほ)もないままに、絶対の弧のうちに、引き受けなければならない。
このとき、それまで陳腐だった第三人称の死の一つずつが、もしかして自分がこれから引き受けようとしている死の先達として、意味をもってくるように思われるかもしれないにせよ、もとよりそれは、空疎な期待にすぎない。
(出典:村上陽一郎『生と死への眼差し』)
【設問】
次の①~④のうち、「私にとっての第三人称の死」を表すものの正しい組み合わせを、A~Eの中から1つ選べ。
①自分以外には架せられないもの
②陳腐なもの
③つねに未来形でしかないもの
④消滅であり消失の過去
例題:
A. ④のみ
B. ②と④
C. ①と②と③
D. ②のみ
E. ①~④全部
①は、「私の死」についての記述。②は第三人称の死のひとつひとつが陳腐であるとある。③は生きている間に自分の死に直面しないため。④は過去の出来事として経験されることである。したがって、②と④。
死に勝る苦しみ、という表現がある。では死は苦しみの極限としてあるのか。そうではあるまい。苦しむのは生である。苦しみは生きていることの一つの証である。生の状態である。死が生の終わりなら、(イ)死は苦しみの終わりでもある。しかし、繰り返すが、私という第一人称にとって、死は、完璧な未知である。本当に死は苦しみの終わりなのかどうか、それを言うことさえ不可能なものとして、死はある。
したがって、いわゆる死への恐怖は、苦しむ生への恐怖を含んでいるにせよ、それだけではあるまい。
生への盲目的な執着が、ヒトが生物であることの明証であるとすれば、死への恐怖はヒトが人間であることの明証であると言えぬだろうか。
第三人称の死は、私にとって、消滅であり、消失であった。したがって、それは、本当の意味での「死」ではない。自分の前に立ちはだかる未知の深淵としての死の何たるかを知ろうとする、空虚(むな)しい努力のための、何らの糧にもならない。自分の万年筆やハンカチや財布をいくら紛失したとしても、それで自分の死について何か感ずるところがあったとは言えまい。
そして、第一人称の死、つねに未来形でしかありえないものが、現実化したとき、「私」は誰からも手助けを受けることなく、完全な孤絶のなかで、それを体験することになる。第三人称の死が、「私」とって消滅であるならば、第三者にとって「私」の死は同じように単なる消滅以外のものではありえないだろう。「私」にとって一度も体験したことのない「私の死」を、私は、自分以外の一切の他に対して架すべき何らかの橋堡(きょうほ)もないままに、絶対の弧のうちに、引き受けなければならない。
このとき、それまで陳腐だった第三人称の死の一つずつが、もしかして自分がこれから引き受けようとしている死の先達として、意味をもってくるように思われるかもしれないにせよ、もとよりそれは、空疎な期待にすぎない。
(出典:村上陽一郎『生と死への眼差し』)
【設問】
(イ)「死は苦しみの終わりでもある」という主張がなぜそのようにいえるのか。A~Eの中から正しいものを1つ選べ。
例題:
A. 死が生きている間は未知のものであり、苦しみの持ちようがないから
B. 生きている間に死への恐怖を感じることで、恐怖心が徐々になくなっていくから
C. 苦しみは生の状態のときに感じるものである。また死が生の終焉ととらえるなら、死によって苦しみは生じ得なくなるから
D. ヒトは生に対する執着を生物と同様に持ち合わせているから
E. 死が未知のものであるため、苦しいものかどうかわかっていないから
「苦しみは生きていることの一つの証である。」から、生きている状態で苦しみは感じると主張。さらに、死が生の終わりであると考えるなら、生きている状態が終わるため、苦しみが発生することはなくなる。
死に勝る苦しみ、という表現がある。では死は苦しみの極限としてあるのか。そうではあるまい。苦しむのは生である。苦しみは生きていることの一つの証である。生の状態である。死が生の終わりなら、死は苦しみの終わりでもある。しかし、繰り返すが、私という第一人称にとって、死は、完璧な未知である。本当に死は苦しみの終わりなのかどうか、それを言うことさえ不可能なものとして、死はある。
したがって、いわゆる死への恐怖は、苦しむ生への恐怖を含んでいるにせよ、それだけではあるまい。
生への盲目的な執着が、ヒトが生物であることの明証であるとすれば、死への恐怖はヒトが人間であることの明証であると言えぬだろうか。
第三人称の死は、私にとって、消滅であり、消失であった。したがって、それは、本当の意味での「死」ではない。自分の前に立ちはだかる未知の深淵としての死の何たるかを知ろうとする、空虚(むな)しい努力のための、何らの糧にもならない。自分の万年筆やハンカチや財布をいくら紛失したとしても、それで自分の死について何か感ずるところがあったとは言えまい。
そして、第一人称の死、つねに未来形でしかありえないものが、現実化したとき、「私」は誰からも手助けを受けることなく、完全な孤絶のなかで、それを( ② )することになる。第三人称の死が、「私」とって消滅であるならば、第三者にとって「私」の死は同じように単なる消滅以外のものではありえないだろう。「私」にとって一度も体験したことのない「私の死」を、私は、自分以外の一切の他に対して架すべき何らかの橋堡(きょうほ)もないままに、絶対の弧のうちに、引き受けなければならない。
このとき、それまで陳腐だった第三人称の死の一つずつが、もしかして自分がこれから引き受けようとしている死の先達として、意味をもってくるように思われるかもしれないにせよ、もとよりそれは、空疎な期待にすぎない。
(出典:村上陽一郎『生と死への眼差し』)
【設問】
文中の( ① )・( ② )に当てはまる言葉を、A~Eの中から1つ選べ。
例題:
( ① )
A. 恐怖
B. 執着
C. 明証
D. 苦しみ
E. 表現
( ② )
A. 消失
B. 恐怖
C. 引き受け
D. 体験
E. 紛失
( ① )A
「それは死への恐怖というよりは」と対比している。
( ② )D
「私」にとって一度も体験したことのない「私の死」は、生の最後の瞬間に体験することになる。
今ここで述べてきたような、音楽の筆記的特性とでも呼び得る性質は、今世紀の前衛音楽によって、単に受け継がれただけでなく、一層推し進められていった。作曲技法における筆記性が強まるだけでなく、同時に、演奏者に「解釈」の自由がほとんど残されていないような「テクスト」が書かれる傾向が促進され、音楽における「テクスト」の優位が絶対視されるようになっていったのである。このような音楽の筆記性は一九五〇年代の前衛音楽でほぼ飽和状態にまで達した――少なくとも、多くの音楽家たちはそう実感していた。そして一九六〇年代後期には、そうした筆記性の飽和への反動として、(ロ)非筆記的な即興演奏へと向かう動きが、突然、急進的な前衛音楽家たちの間に広がり始める。そうした即興演奏とは、正に、演奏する奏者同士の間で行われる音響を媒介とした口述的コミュニケーションを主眼とした音楽である。演奏の現場で直に、演奏に参加している全員によって作られるその音楽には、書き記された「テクスト」といったものは存在せず、したがって、「テクスト」の作者としての「作曲者」というものもない。強いて言えば、そこでの演奏者全員がそのまま同時にその音楽の作曲者であって、その音楽は、つまり、「個人」の名をもっていないのである――音楽は、「無名性」を獲得するのだ。
(出典:近藤譲『音を投げる 作曲思想の射程』)
【設問】
(ロ)非筆記的な即興演奏を表さないものを、次のA~Eから1つ選べ。
例題:
A. 演奏する奏者同士の間で行われる音響を媒体としたコミュニケーション
B. 音楽における「テクスト」の優位の絶対視
C. 筆記性の飽和への反動
D. 「テクスト」といったものは存在しない
E. 「作曲者」というものがない
A.「テクスト」としての楽譜がないため、奏者とのコミュニケーションによるところが大きい。
B.音楽には「テクスト」が重要であるとする見方。これは即興演奏を意味しない。
C.筆記性に依存した音楽で満ちたため、新しい音楽として即興演奏が生まれた。
D.「テクスト」に頼らない音楽が即興演奏である。
E.作曲者の考えたとおりの演奏ではなく、即興演奏は、そのときの奏者の演奏によるため、作曲者がいるわけではない。
今ここで述べてきたような、音楽の筆記的特性とでも呼び得る性質は、今世紀の前衛音楽によって、単に受け継がれただけでなく、一層推し進められていった。作曲技法における筆記性が強まるだけでなく、同時に、演奏者に「解釈」の自由がほとんど残されていないような「テクスト」が書かれる傾向が促進され、音楽における「テクスト」の優位が絶対視されるようになっていったのである。このような音楽の筆記性は一九五〇年代の前衛音楽でほぼ飽和状態にまで達した――少なくとも、多くの音楽家たちはそう実感していた。そして一九六〇年代後期には、そうした筆記性の飽和への反動として、非筆記的な即興演奏へと向かう動きが、突然、急進的な前衛音楽家たちの間に広がり始める。そうした即興演奏とは、正に、演奏する奏者同士の間で行われる音響を媒介とした口述的コミュニケーションを主眼とした音楽である。演奏の現場で直に、演奏に参加している全員によって作られるその音楽には、書き記された「テクスト」といったものは存在せず、したがって、「テクスト」の作者としての「作曲者」というものもない。強いて言えば、そこでの演奏者全員がそのまま同時にその音楽の作曲者であって、その音楽は、つまり、「個人」の名をもっていないのである――音楽は、「無名性」を獲得するのだ。
(出典:近藤譲『音を投げる 作曲思想の射程』)
【設問】
(イ)「紙に記された楽譜は、実際の演奏によって音響として実現されない限り、いまだ音楽ではない。」であるのはなぜかを表す、次の文章の( )に適する言葉の正しい組み合わせはどれか。
作曲家が提示する楽譜は、そのままでは音楽作品の「テクスト」に過ぎず、演奏者によって解釈され音響化され( )を得ることで、はじめて音楽作品になるということ。
例題:
A. 現実
B. 実物
C. 実写
D. 事実
E. 実体
「テクスト」としての楽譜があることで、演奏する方法を実現できる。楽譜はあくまでもその方法を示すものであり、奏者が実際に音楽を奏でることによって、その音楽が実際の形となる。したがって最も当てはまるのは「実体」である。
今ここで述べてきたような、音楽の筆記的特性とでも呼び得る性質は、今世紀の前衛音楽によって、単に受け継がれただけでなく、一層推し進められていった。作曲技法における筆記性が強まるだけでなく、同時に、演奏者に「解釈」の自由がほとんど残されていないような「テクスト」が書かれる傾向が促進され、音楽における「テクスト」の優位が絶対視されるようになっていったのである。このような音楽の筆記性は一九五〇年代の前衛音楽でほぼ飽和状態にまで達した――少なくとも、多くの音楽家たちはそう実感していた。そして一九六〇年代後期には、そうした筆記性の飽和への反動として、非筆記的な即興演奏へと向かう動きが、突然、急進的な前衛音楽家たちの間に広がり始める。そうした即興演奏とは、正に、演奏する奏者同士の間で行われる音響を媒介とした( ① )コミュニケーションを主眼とした音楽である。演奏の現場で直に、演奏に参加している全員によって作られるその音楽には、書き記された「テクスト」といったものは存在せず、したがって、「テクスト」の作者としての「作曲者」というものもない。強いて言えば、そこでの演奏者全員がそのまま同時にその音楽の作曲者であって、その音楽は、つまり、「個人」の名をもっていないのである――音楽は、「( ② )」を獲得するのだ。
(出典:近藤譲『音を投げる 作曲思想の射程』)
【設問】
文中の( ① )・( ② )に当てはまる言葉の組み合わせで正しいものを選べ。
例題:
A. ①筆記的 ②無名性
B. ①記録的 ②有名性
C. ①筆記的 ②有名性
D. ①口述的 ②無名性
E. ①口述的 ②有名性
①即興演奏は非筆記的である。
②テクストが存在しない中での音楽は、誰かが作曲・演奏したとおりにする必要はなく、あくまでも演奏者のその時の演奏が全てである。よって無名性の音楽といえる。