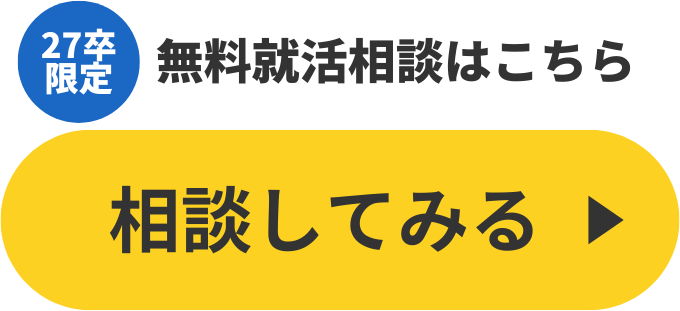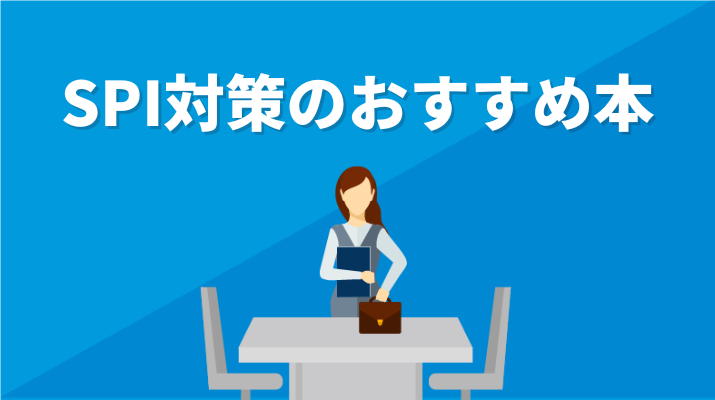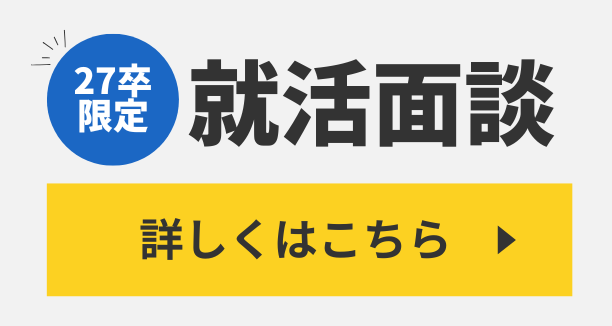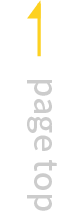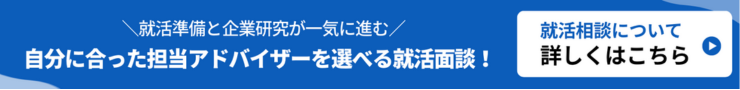彼女は数学を解くのが得意だ。
例題:
A. この小説は面白い。
B. 彼は言語を学ぶのが速い。
C. その試験は難しい。
D. 私はスポーツをするのが楽しい。
E. あの山は高い。
「~するのが~だ」は能力や特性を表す用法ですが、この文脈では「得意」という特性に対して、「速い」という特性が言及されています。したがって、Bが最適な選択肢です。Aは「面白い」という異なる特性を示しており、C、D、Eは文脈に合っていない表現です。
このような自然科学の知は、「自分」を環境から切り離して得たものであるから、誰に対しても普遍的に通用する点で、大きい強みを持っている。自然科学の知はどこでも通用する。しかし、ここで一旦切り離した自分を、全体のなかに入れ、自分という存在とのかかわりで考えてみるとどうなるか。なぜ、自分はこのような太陽の運行と関連する地球に住んでいるのか。自分は何のために生きているのか、などと考えはじめるとき、自然科学の知は役に立たない。それは出発の最初から、自分を抜きにして得たものなのだから、当然のことである。太陽の動きや、はたらきは、自分と無関係に説明できる。しかし、他ならぬ自分という存在と、太陽とは、どうかかわるか。
太陽と自分とのかかわりについて、確たる知を持って生きている人たちについて、ユングは彼の自伝のなかで述べている。ユングが旅をしてプエブロ・インディアンを訪ねて行ったときのことである。インディアンたちは、彼らの宗教的儀式や祈りによって、太陽が天空を運行するのを助けていると言うのである。「われわれは世界の屋根に住んでいる人間なのだ。われわれは太陽の息子たち。そしてわれらの宗教によって、われわれは毎日、われらの父が天空を横切る手伝いをしている。それはわれわれのためばかりでなく、全世界のためなんだ」とインディアンの一人は語った。彼らは全世界のため太陽の息子としての勤めを果たしていると確信している。これに対して、ユングは次のように『自伝』の中で述べている。
「そのとき、私は一人一人のインディアンにみられる、静かなたたずまいと『気品』のようなものがなにに由来するのかが分かった。それは太陽の息子ということから生じてくる。彼の生活が宇宙論的意味を帯びているのは、彼が父なる太陽の、つまり生命全体の保護者の、日毎の出没を助けているからである」
インディアンたちは彼らの「神話の知」を生きることによって、ユングが羨望を禁じ得ない「気品」をもって生きている。これに対して、近代人は何とせかせかと生きていることか。近代人は豊かな科学の知と、極めて貧困な精神とをもって生きている。
(出典:河合隼雄『イメージの心理学』)
【設問】
文章の内容と一致するものを、次のA~Eの中から1つ選べ。
例題:
A. 現代人にとって自然科学の知は、人によって異なる、扱いにくいものである
B. 自分が生きる意義を考えるとき、自然科学の知は役に立たない
C. インディアンは、自然と自分との関わりという概念を持っていない
D. 現代人は、自分たちを太陽の息子たちととらえて生きている
E. 現代人がせかせかと生きている原因は、宇宙論的意味を得ているからである
自然科学をとらえる際、人間は自身の存在を切り離して観察するため、自然や世界、命の問題と自分自身との関わりを持てなくなっているから。
このような自然科学の知は、「自分」を環境から切り離して得たものであるから、誰に対しても普遍的に通用する点で、大きい強みを持っている。自然科学の知はどこでも通用する。しかし、ここで一旦切り離した自分を、全体のなかに入れ、自分という存在とのかかわりで考えてみるとどうなるか。なぜ、自分はこのような太陽の運行と関連する地球に住んでいるのか。自分は何のために生きているのか、などと考えはじめるとき、自然科学の知は役に立たない。それは出発の最初から、自分を抜きにして得たものなのだから、当然のことである。太陽の動きや、はたらきは、自分と無関係に説明できる。しかし、他ならぬ自分という存在と、太陽とは、どうかかわるか。
太陽と自分とのかかわりについて、(イ)確たる知を持って生きている人たちについて、ユングは彼の自伝のなかで述べている。ユングが旅をしてプエブロ・インディアンを訪ねて行ったときのことである。インディアンたちは、彼らの宗教的儀式や祈りによって、太陽が天空を運行するのを助けていると言うのである。「われわれは世界の屋根に住んでいる人間なのだ。われわれは太陽の息子たち。そしてわれらの宗教によって、われわれは毎日、われらの父が天空を横切る手伝いをしている。それはわれわれのためばかりでなく、全世界のためなんだ」とインディアンの一人は語った。彼らは全世界のため太陽の息子としての勤めを果たしていると確信している。これに対して、ユングは次のように『自伝』の中で述べている。
「そのとき、私は一人一人のインディアンにみられる、静かなたたずまいと『気品』のようなものがなにに由来するのかが分かった。それは太陽の息子ということから生じてくる。彼の生活が宇宙論的意味を帯びているのは、彼が父なる太陽の、つまり生命全体の保護者の、日毎の出没を助けているからである」
インディアンたちは彼らの「神話の知」を生きることによって、ユングが羨望を禁じ得ない「気品」をもって生きている。これに対して、近代人は何とせかせかと生きていることか。近代人は豊かな科学の知と、極めて貧困な精神とをもって生きている。
(出典:河合隼雄『イメージの心理学』)
【設問】
(イ)「確たる知」の説明について最も適したものを次のA~Eの中から1つ選べ。
例題:
A. 太陽が天空を運行しているということ
B. 太陽の動きや働きを、自分と無関係に説明できること
C. 自分たちが世界の屋根に住む人間だと自覚していること
D. 全世界のため、太陽の息子としての勤めを果たしていること
E. 自分たちが静かなたたずまいと気品を持っているということ
確たる知は、本人たちの中で確信を持ったものである。それがDの内容である。
このような自然科学の知は、「自分」を環境から切り離して得たものであるから、誰に対しても普遍的に通用する点で、大きい強みを持っている。自然科学の知はどこでも通用する。しかし、ここで一旦切り離した自分を、全体のなかに入れ、自分という存在とのかかわりで考えてみるとどうなるか。なぜ、自分はこのような太陽の運行と関連する地球に住んでいるのか。自分は何のために生きているのか、などと考えはじめるとき、自然科学の知は役に立たない。それは出発の最初から、自分を抜きにして得たものなのだから、当然のことである。太陽の動きや、はたらきは、自分と無関係に説明できる。しかし、他ならぬ自分という存在と、太陽とは、どうかかわるか。
太陽と自分とのかかわりについて、確たる知を持って生きている人たちについて、ユングは彼の自伝のなかで述べている。ユングが旅をしてプエブロ・インディアンを訪ねて行ったときのことである。インディアンたちは、彼らの宗教的儀式や祈りによって、太陽が天空を運行するのを助けていると言うのである。「われわれは世界の屋根に住んでいる人間なのだ。われわれは太陽の息子たち。そしてわれらの宗教によって、われわれは毎日、われらの父が天空を横切る手伝いをしている。それはわれわれのためばかりでなく、全世界のためなんだ」とインディアンの一人は語った。彼らは全世界のため太陽の息子としての勤めを果たしていると確信している。これに対して、ユングは次のように『自伝』の中で述べている。
「そのとき、私は一人一人のインディアンにみられる、静かなたたずまいと『気品』のようなものがなにに由来するのかが分かった。それは太陽の息子ということから生じてくる。彼の生活が宇宙論的意味を帯びているのは、彼が父なる太陽の、つまり生命全体の保護者の、日毎の出没を助けているからである」
インディアンたちは彼らの「神話の知」を生きることによって、ユングが羨望を禁じ得ない「気品」をもって生きている。これに対して、近代人は何とせかせかと生きていることか。近代人は豊かな科学の知と、極めて貧困な精神とをもって生きている。
(出典:河合隼雄『イメージの心理学』)
【設問】
文中の( ① )に当てはまる言葉を、次のA~Eの中から1つ選べ。
例題:
A. 経験
B. 技術
C. 知識
D. 能力
E. 情報
「自然科学の知」についての言及であるから、最終目標は知である。
死に勝る苦しみ、という表現がある。では死は苦しみの極限としてあるのか。そうではあるまい。苦しむのは生である。苦しみは生きていることの一つの証である。生の状態である。死が生の終わりなら、死は苦しみの終わりでもある。しかし、繰り返すが、私という第一人称にとって、死は、完璧な未知である。本当に死は苦しみの終わりなのかどうか、それを言うことさえ不可能なものとして、死はある。
したがって、いわゆる死への恐怖は、苦しむ生への恐怖を含んでいるにせよ、それだけではあるまい。
生への盲目的な執着が、ヒトが生物であることの明証であるとすれば、死への恐怖はヒトが人間であることの明証であると言えぬだろうか。
第三人称の死は、私にとって、消滅であり、消失であった。したがって、それは、本当の意味での「死」ではない。自分の前に立ちはだかる未知の深淵としての死の何たるかを知ろうとする、空虚(むな)しい努力のための、何らの糧にもならない。自分の万年筆やハンカチや財布をいくら紛失したとしても、それで自分の死について何か感ずるところがあったとは言えまい。
そして、第一人称の死、つねに未来形でしかありえないものが、現実化したとき、「私」は誰からも手助けを受けることなく、完全な孤絶のなかで、それを体験することになる。第三人称の死が、「私」とって消滅であるならば、第三者にとって「私」の死は同じように単なる消滅以外のものではありえないだろう。「私」にとって一度も体験したことのない「私の死」を、私は、自分以外の一切の他に対して架すべき何らかの橋堡(きょうほ)もないままに、絶対の弧のうちに、引き受けなければならない。
このとき、それまで陳腐だった第三人称の死の一つずつが、もしかして自分がこれから引き受けようとしている死の先達として、意味をもってくるように思われるかもしれないにせよ、もとよりそれは、空疎な期待にすぎない。
(出典:村上陽一郎『生と死への眼差し』)
【設問】
次の①~④のうち、「私にとっての第三人称の死」を表すものの正しい組み合わせを、A~Eの中から1つ選べ。
①自分以外には架せられないもの
②陳腐なもの
③つねに未来形でしかないもの
④消滅であり消失の過去
例題:
A. ④のみ
B. ②と④
C. ①と②と③
D. ②のみ
E. ①~④全部
①は、「私の死」についての記述。②は第三人称の死のひとつひとつが陳腐であるとある。③は生きている間に自分の死に直面しないため。④は過去の出来事として経験されることである。したがって、②と④。
死に勝る苦しみ、という表現がある。では死は苦しみの極限としてあるのか。そうではあるまい。苦しむのは生である。苦しみは生きていることの一つの証である。生の状態である。死が生の終わりなら、(イ)死は苦しみの終わりでもある。しかし、繰り返すが、私という第一人称にとって、死は、完璧な未知である。本当に死は苦しみの終わりなのかどうか、それを言うことさえ不可能なものとして、死はある。
したがって、いわゆる死への恐怖は、苦しむ生への恐怖を含んでいるにせよ、それだけではあるまい。
生への盲目的な執着が、ヒトが生物であることの明証であるとすれば、死への恐怖はヒトが人間であることの明証であると言えぬだろうか。
第三人称の死は、私にとって、消滅であり、消失であった。したがって、それは、本当の意味での「死」ではない。自分の前に立ちはだかる未知の深淵としての死の何たるかを知ろうとする、空虚(むな)しい努力のための、何らの糧にもならない。自分の万年筆やハンカチや財布をいくら紛失したとしても、それで自分の死について何か感ずるところがあったとは言えまい。
そして、第一人称の死、つねに未来形でしかありえないものが、現実化したとき、「私」は誰からも手助けを受けることなく、完全な孤絶のなかで、それを体験することになる。第三人称の死が、「私」とって消滅であるならば、第三者にとって「私」の死は同じように単なる消滅以外のものではありえないだろう。「私」にとって一度も体験したことのない「私の死」を、私は、自分以外の一切の他に対して架すべき何らかの橋堡(きょうほ)もないままに、絶対の弧のうちに、引き受けなければならない。
このとき、それまで陳腐だった第三人称の死の一つずつが、もしかして自分がこれから引き受けようとしている死の先達として、意味をもってくるように思われるかもしれないにせよ、もとよりそれは、空疎な期待にすぎない。
(出典:村上陽一郎『生と死への眼差し』)
【設問】
(イ)「死は苦しみの終わりでもある」という主張がなぜそのようにいえるのか。A~Eの中から正しいものを1つ選べ。
例題:
A. 死が生きている間は未知のものであり、苦しみの持ちようがないから
B. 生きている間に死への恐怖を感じることで、恐怖心が徐々になくなっていくから
C. 苦しみは生の状態のときに感じるものである。また死が生の終焉ととらえるなら、死によって苦しみは生じ得なくなるから
D. ヒトは生に対する執着を生物と同様に持ち合わせているから
E. 死が未知のものであるため、苦しいものかどうかわかっていないから
「苦しみは生きていることの一つの証である。」から、生きている状態で苦しみは感じると主張。さらに、死が生の終わりであると考えるなら、生きている状態が終わるため、苦しみが発生することはなくなる。
死に勝る苦しみ、という表現がある。では死は苦しみの極限としてあるのか。そうではあるまい。苦しむのは生である。苦しみは生きていることの一つの証である。生の状態である。死が生の終わりなら、死は苦しみの終わりでもある。しかし、繰り返すが、私という第一人称にとって、死は、完璧な未知である。本当に死は苦しみの終わりなのかどうか、それを言うことさえ不可能なものとして、死はある。
したがって、いわゆる死への恐怖は、苦しむ生への恐怖を含んでいるにせよ、それだけではあるまい。
生への盲目的な執着が、ヒトが生物であることの明証であるとすれば、死への恐怖はヒトが人間であることの明証であると言えぬだろうか。
第三人称の死は、私にとって、消滅であり、消失であった。したがって、それは、本当の意味での「死」ではない。自分の前に立ちはだかる未知の深淵としての死の何たるかを知ろうとする、空虚(むな)しい努力のための、何らの糧にもならない。自分の万年筆やハンカチや財布をいくら紛失したとしても、それで自分の死について何か感ずるところがあったとは言えまい。
そして、第一人称の死、つねに未来形でしかありえないものが、現実化したとき、「私」は誰からも手助けを受けることなく、完全な孤絶のなかで、それを( ② )することになる。第三人称の死が、「私」とって消滅であるならば、第三者にとって「私」の死は同じように単なる消滅以外のものではありえないだろう。「私」にとって一度も体験したことのない「私の死」を、私は、自分以外の一切の他に対して架すべき何らかの橋堡(きょうほ)もないままに、絶対の弧のうちに、引き受けなければならない。
このとき、それまで陳腐だった第三人称の死の一つずつが、もしかして自分がこれから引き受けようとしている死の先達として、意味をもってくるように思われるかもしれないにせよ、もとよりそれは、空疎な期待にすぎない。
(出典:村上陽一郎『生と死への眼差し』)
【設問】
文中の( ① )・( ② )に当てはまる言葉を、A~Eの中から1つ選べ。
例題:
( ① )
A. 恐怖
B. 執着
C. 明証
D. 苦しみ
E. 表現
( ② )
A. 消失
B. 恐怖
C. 引き受け
D. 体験
E. 紛失
( ① )A
「それは死への恐怖というよりは」と対比している。
( ② )D
「私」にとって一度も体験したことのない「私の死」は、生の最後の瞬間に体験することになる。
今ここで述べてきたような、音楽の筆記的特性とでも呼び得る性質は、今世紀の前衛音楽によって、単に受け継がれただけでなく、一層推し進められていった。作曲技法における筆記性が強まるだけでなく、同時に、演奏者に「解釈」の自由がほとんど残されていないような「テクスト」が書かれる傾向が促進され、音楽における「テクスト」の優位が絶対視されるようになっていったのである。このような音楽の筆記性は一九五〇年代の前衛音楽でほぼ飽和状態にまで達した――少なくとも、多くの音楽家たちはそう実感していた。そして一九六〇年代後期には、そうした筆記性の飽和への反動として、(ロ)非筆記的な即興演奏へと向かう動きが、突然、急進的な前衛音楽家たちの間に広がり始める。そうした即興演奏とは、正に、演奏する奏者同士の間で行われる音響を媒介とした口述的コミュニケーションを主眼とした音楽である。演奏の現場で直に、演奏に参加している全員によって作られるその音楽には、書き記された「テクスト」といったものは存在せず、したがって、「テクスト」の作者としての「作曲者」というものもない。強いて言えば、そこでの演奏者全員がそのまま同時にその音楽の作曲者であって、その音楽は、つまり、「個人」の名をもっていないのである――音楽は、「無名性」を獲得するのだ。
(出典:近藤譲『音を投げる 作曲思想の射程』)
【設問】
(ロ)非筆記的な即興演奏を表さないものを、次のA~Eから1つ選べ。
例題:
A. 演奏する奏者同士の間で行われる音響を媒体としたコミュニケーション
B. 音楽における「テクスト」の優位の絶対視
C. 筆記性の飽和への反動
D. 「テクスト」といったものは存在しない
E. 「作曲者」というものがない
A.「テクスト」としての楽譜がないため、奏者とのコミュニケーションによるところが大きい。
B.音楽には「テクスト」が重要であるとする見方。これは即興演奏を意味しない。
C.筆記性に依存した音楽で満ちたため、新しい音楽として即興演奏が生まれた。
D.「テクスト」に頼らない音楽が即興演奏である。
E.作曲者の考えたとおりの演奏ではなく、即興演奏は、そのときの奏者の演奏によるため、作曲者がいるわけではない。
今ここで述べてきたような、音楽の筆記的特性とでも呼び得る性質は、今世紀の前衛音楽によって、単に受け継がれただけでなく、一層推し進められていった。作曲技法における筆記性が強まるだけでなく、同時に、演奏者に「解釈」の自由がほとんど残されていないような「テクスト」が書かれる傾向が促進され、音楽における「テクスト」の優位が絶対視されるようになっていったのである。このような音楽の筆記性は一九五〇年代の前衛音楽でほぼ飽和状態にまで達した――少なくとも、多くの音楽家たちはそう実感していた。そして一九六〇年代後期には、そうした筆記性の飽和への反動として、非筆記的な即興演奏へと向かう動きが、突然、急進的な前衛音楽家たちの間に広がり始める。そうした即興演奏とは、正に、演奏する奏者同士の間で行われる音響を媒介とした口述的コミュニケーションを主眼とした音楽である。演奏の現場で直に、演奏に参加している全員によって作られるその音楽には、書き記された「テクスト」といったものは存在せず、したがって、「テクスト」の作者としての「作曲者」というものもない。強いて言えば、そこでの演奏者全員がそのまま同時にその音楽の作曲者であって、その音楽は、つまり、「個人」の名をもっていないのである――音楽は、「無名性」を獲得するのだ。
(出典:近藤譲『音を投げる 作曲思想の射程』)
【設問】
(イ)「紙に記された楽譜は、実際の演奏によって音響として実現されない限り、いまだ音楽ではない。」であるのはなぜかを表す、次の文章の( )に適する言葉の正しい組み合わせはどれか。
作曲家が提示する楽譜は、そのままでは音楽作品の「テクスト」に過ぎず、演奏者によって解釈され音響化され( )を得ることで、はじめて音楽作品になるということ。
例題:
A. 現実
B. 実物
C. 実写
D. 事実
E. 実体
「テクスト」としての楽譜があることで、演奏する方法を実現できる。楽譜はあくまでもその方法を示すものであり、奏者が実際に音楽を奏でることによって、その音楽が実際の形となる。したがって最も当てはまるのは「実体」である。
今ここで述べてきたような、音楽の筆記的特性とでも呼び得る性質は、今世紀の前衛音楽によって、単に受け継がれただけでなく、一層推し進められていった。作曲技法における筆記性が強まるだけでなく、同時に、演奏者に「解釈」の自由がほとんど残されていないような「テクスト」が書かれる傾向が促進され、音楽における「テクスト」の優位が絶対視されるようになっていったのである。このような音楽の筆記性は一九五〇年代の前衛音楽でほぼ飽和状態にまで達した――少なくとも、多くの音楽家たちはそう実感していた。そして一九六〇年代後期には、そうした筆記性の飽和への反動として、非筆記的な即興演奏へと向かう動きが、突然、急進的な前衛音楽家たちの間に広がり始める。そうした即興演奏とは、正に、演奏する奏者同士の間で行われる音響を媒介とした( ① )コミュニケーションを主眼とした音楽である。演奏の現場で直に、演奏に参加している全員によって作られるその音楽には、書き記された「テクスト」といったものは存在せず、したがって、「テクスト」の作者としての「作曲者」というものもない。強いて言えば、そこでの演奏者全員がそのまま同時にその音楽の作曲者であって、その音楽は、つまり、「個人」の名をもっていないのである――音楽は、「( ② )」を獲得するのだ。
(出典:近藤譲『音を投げる 作曲思想の射程』)
【設問】
文中の( ① )・( ② )に当てはまる言葉の組み合わせで正しいものを選べ。
例題:
A. ①筆記的 ②無名性
B. ①記録的 ②有名性
C. ①筆記的 ②有名性
D. ①口述的 ②無名性
E. ①口述的 ②有名性
①即興演奏は非筆記的である。
②テクストが存在しない中での音楽は、誰かが作曲・演奏したとおりにする必要はなく、あくまでも演奏者のその時の演奏が全てである。よって無名性の音楽といえる。
ところで覆面というのは、自分の顔を覆って、( 1 )を隠したまま、他者を見るための装具である。私を他者の視線から遮る一枚の布によって、その布の両側にいる二人の人間が、見るが見られない人と、見られるが見返せない人とに分割される。覆面越しに見られた人は、見る人の( 2 )を確認できても、それが誰であるかを突き止めることはできないのだ。
例題:
A. 1.名前 2.性別
B. 1.目 2.性別
C. 1.目 2.声
D. 1.素性 2.声
E. 1.素性 2.存在
F. 1.名前 2.存在
名前はどこにも登場しない。覆面はむしろ視界は確保する必要があるため、目を覆うことは不可能である。また、覆面越しに見られた人は、顔はわからなくとも、そこに人がいるということは認知できる。
これだけ苦労しても、書いた文章に言葉の( 1 )はまだあるもので、それを削る。単語に関していえば、( 2 )になりがちな語の筆頭は形容詞と( 2 )、とくに( 2 )で、中でも「たいへん」とか「非常に」とかいうのは、ほとんどの場合捨てることができる。こうして言葉を削って、このことについてこれだけの字数で言うにはこう書くほかは書きようがない、というところまでもっていく、つまり抜き差しならぬ文章を仕上げる。
例題:
A. 1.むだ 2.形容動詞
B. 1.むだ 2.副詞
C. 1.間違い 2.助動詞
D. 1.間違い 2.副詞
E. 1.誤用 2.助動詞
F. 1.誤用 2.形容動詞
間違いや誤用であれば「訂正」や「修正」になるのであって、削ることはない。また、「たいへん」や「非常に」は動詞を修飾するので副詞である。
見習いの機能が生きていた時代には、大人は、たとえ子供を理解しないままでも、( 1 )を養成することができた。それとは対照的に、近代の学校教師は、子どもを( 2 )に育てあげる能力をほとんど失ったにもかかわらず、いや失ったがゆえに、子どもへの理解を無限に強いられる。
例題:
A. 1.後継者 2.教師
B. 1.指導者 2.教師
C. 1.後継者 2.社会人
D. 1.指導者 2.社会人
E. 1.後継者 2.職人
F. 1.指導者 2.職人
見習いが存在していた時代の場合は、次に続く職人を育成していた。また、現代は学校の教師は、子どもを社会人に育てるべく、さまざまな知識などを教えようとするが、さまざまな課題を抱えている。
伝統に歴史は必要であるとしても、歴史はそのまま伝統ではない。単に無意識のまま受け伝えられてきたものは、( 1 )と呼ばれるにさわしいものであって、まだ( 2 )ではない。( 2 )は、それと意識されることによって初めて( 2 )となる。古くから伝えられてきたものが一つのモデルないしは手本として意識された時に( 2 )というものになるのである。
例題:
A. 1.伝承 2.文化
B. 1.伝統 2.文化
C. 1.伝承 2.芸術
D. 1.伝統 2.芸術
E. 1.伝統 2.歴史
F. 1.伝承 2.伝統
単純に伝えるだけでは「伝承」であり、それを守る価値を見出し、強い意識をもって後世にも伝えようとしたときにそれははじめて伝統となる。
多くの論者が指摘しているように、ディズニーランドという空間の顕著な特徴は、それが、完璧に( 1 )された空間であって、( 2 )な内部を形成している、ということである。ディズニーランドは、外的空間から効果的に遮断されているだけではなく、まさに遮断されているという事実からも遮断されている。
例題:
A. 1.遮蔽 2.自立的
B. 1.開放 2.自立的
C. 1.遮蔽 2.幻想的
D. 1.開放 2.幻想的
E. 1.遮蔽 2.虚構的
F. 1.開放 2.虚構的
ディズニーランドは遮断されているという主張が後半で出てくる。また、遮断されるために、訪れた人々は外側の世界を意識することなく、ディズニーランド独自の世界観を楽しめる。その世界観で完結できるところが特徴である。
私たちの「運命への関心」は、科学が発達したからといって消え去りはしない。この関心に対しては確率論も無力である。確率的な予測は、( 1 )の観測を仮定してはじめて成り立つ。しかし人生において私たちは決して( 1 )のトライアルを許されてはいない。むしろ特定のただ一回のトライアルが問題なのだ。その( 2 )の挑戦でどの目が出るか、そこにすべての運命がかかっている。
例題:
A. 1.無限回 2.積み重ね
B. 1.計算上 2.一回限り
C. 1.一回 2.無限回
D. 1.無限回 2.一回限り
E. 1.一回 2.積み重ね
F. 1.計算上 2.無限回
確率は、少数回の試行では、そのときの偶然に左右されるため、試行は無限回に近づけるほど、計算上の確率に近づくことが知られている。しかし、実際の人生における出来事は、無限回の試行はできないし、むしろたった一回のイレギュラーで事態は大きく変わってしまうものだ。
その技術には( )的な人が多かった。
例題:
A. 懐疑
B. 疑念
C. 疑惑
D. 質疑
E. 疑問
それが本当か疑わしいこと。後ろに「的」がつくのは懐疑のみ。
ニュースを見て、事故に遭った人の( )を気遣う
例題:
A. 安堵
B. 安心
C. 安全
D. 安否
E. 安息
「安否」は無事かどうかという意味。「安全」も近いが、「気遣う」につなげることを見れば、安否がより適している。
うがいの( )が風邪の予防になる。
例題:
A. 奨励
B. 遵守
C. 激励
D. 敢行
「奨励」は人にすすめること。「遵守」は決まりや法令などを守るという意味であり、習慣に対しては用いない。「敢行」は思い切って行動すること。「慣行」であれば( )に適切なことばとなっていた。
彼の熱いスピーチに、私は深く( )を受けた。
例題:
A. 感動
B. 感心
C. 感銘
D. 琴線
E. 感慨
一般的には「感動する」「感動を覚える」「感心する」「琴線に触れる」「感慨にふける」を使う。
彼は、常に( ) を忘れず、周囲に親切に接していた。
例題:
A. 礼節
B. 礼儀
C. 礼貌
D. 所作
E. 作法
「忘れない」に続く言葉は「礼節」。礼儀は「礼儀正しい」というのが一般的。
ア 「非科学的」「非合理的」ということで
イ 古来からある神話や昔話を
ウ その意義を見直してみることが必要であろう
エ その本来の目的に沿った形で
オ 簡単に排斥するのではなく
例題:
A. オとエ
B. アとオ
C. ウとエ
D. オとイ
E. アとウ
「~するのではなく」「~してみることが必要であろう」の流れを作るとよい。イ→ア→オは自然に作ることができる。ウやエの「その」という指示語は文の後半で使用する事が多い。それにより、イアオエウとなる。
ア その仕事を見習いながら
イ それぞれの仕事が行われている現場において
ウ 産業革命以前の大部分の子どもは、学校においてではなく
エ 一人前の大人となった
オ 親か親代わりの大人の仕事の後継者として
例題:
A. イとエ
B. ウとイ
C. オとウ
D. アとオ
E. イとオ
主語は「産業革命以前の大部分の子ども」、述語は「一人前の大人となった」。「学校においてではなく」の後に、それを否定する異なった部分が入る。学校を否定するため、同じく場所について言及をしていることからウ→イとなる。これらのことから、ウイオアエとなる。
ア この小説が、抵抗運動についてだけ書かれたものだったら
イ 目のさめる思いであの本を読んだのは
ウ 根本のところで提示されているように思えたからだった
エ たぶん、あれほど私たちを興奮させはしなかっただろう
オ そこに「人間らしく生きる」とはなにかという問題が
例題:
A. エとイ
B. ウとア
C. エとオ
D. ウとエ
E. イとオ
アは「だったら」と仮定を意味する言葉で終わっており、エの「だろう」と呼応している。さらに、ウは「思えたからだった」と、動作の理由を示している。それがイの理由と考えられる。したがって、アエイオウとなる。
ア 草花にとまっているときは
イ 曲線的にゆらゆら飛ぶ蝶は
ウ 用心しなければならない
エ 鳥に空中でやすやすと捕らえられることはないというが
オ 飛ぶ方向を急には変えることのできない
例題:
A. オとエ
B. ウとア
C. アとウ
D. オとア
E. ウとイ
「というが」という逆説があるので、エの後ろにはその逆の主張が入る。また「捕らえられることはない」の反対の表現が「用心しなければならない」となるため、エの後ろにウがくる。またその主語は「蝶」であるため、先頭はイ。これらのことから、イ→エ→ア→ウの流れはつかめる。さらにオの「急には変えることのできない」の主体が蝶であるならば、「変えることは(が)できない」となるため、オの直後にはそれを指す名詞が来る。したがって、イオエアウとなる。
ア 必ずしも科学への疑いや不信の表現ではない
イ そのうえに栄えているものだ
ウ むしろ暗黙の科学信仰を前提とし
エ オカルティズムの流行は
オ とくに都市的な大衆文化としてのそれは
例題:
A. ウとア
B. ウとイ
C. エとオ
D. アとオ
E. エとイ
文の書き出しの主語として考えられるのは、「オカルティズムの流行」か「都市的な大衆文化としてのそれ」に絞られるが、「とくに」という接続詞を考えると、前者が文の最初の主語であると判断できる。そうすれば、エ→アの流れが考えられる。そうすれば、都市的な大衆文化としての「それ」は、オカルティズムの流行を指し、その説明がウおよびイとなるため、エアオウイとなる。
ア その体系は、むろん
イ ないし解釈の体系が要請される
ウ 科学の体系とは別に
エ 私たちへの運命への関心に対応する説明
オ 科学的な因果分析とはちがった観点を採用する
例題:
A. イとア
B. エとイ
C. ウとオ
D. アとエ
E. エとウ
「その体系」は「体系」を受けているため、アはウの後ろだが直結はしない。次に「ないし」は並列の意味があるため、「解釈の体系」という名詞が「ないし」の前に来るため、エ→イとなる。そのため、ウエイアオとなる。
われわれは[1][2][3][4][5]いわばクセになっている。
A その「原因」を探して説明し理解しようとする
B 「結果」は必ず「原因」をもつと確信し
C なにか出来事が生じると
D 原因と結果をつないで
E 連続的に歴史をつくるのが
例題:
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E
この文も2つの文からなると考えられる。1文目の最後がAであるが、Aの先頭の「その」が指すものが頭にあるはずなので、それをCと考える。また、「原因」と「結果」との折り合いをつける作業の説明が、B→Dと続くことがわかる。さらにその結末はEであるので、正しい順番は、CABDEである。
古代エジプト人たちは[1][2][3][4][5]描かれているのである。
A しかもその横顔には
B ほとんど三千年ものあいだ
C ご丁寧に正面から見た眼が
D 顔と下半身は横向きで上半身は正面向きという
E われわれから見れば不自然な人間像を描き続けた
例題:
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E
Eの「われわれから見れば不自然な人間像」とは、Dの内容を指すことがわかる。そうすると、D→Eの流れができ、ここで1つの文が終止する。そして、Aの「しかも」は、全文を受ける形が自然であるため、2つ目の文に入れるのが自然。そうすれば、Cが最後となる。さらに残ったBは先頭に来るのが最も良い。したがって、正しい順番は、BDEACである。
どの項目についても[1][2][3][4][5]決めることになる。
A まずはじめに
B これは何を書かずにおくかということと裏腹の課題で
C これだけはぜひ言わなければならないことは何かを
D 何を書くかを決めるわけだが
E 実際には、どんなに手短に言うにしても
例題:
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E
BとDの主張が逆になっているのを「裏腹」と表現しているので、D→Bの流れを作る。しかもこれはまずはじめに行う作業であり、先頭がAとなる。次に、最後の部分の接続を考えると、Cが最後に来る。したがって、正しい順番は、ADBECである。
古くから伝えられてきて[1][2][3][4][5]時である。
A それが失われた時か
B あるいは少なくとも失われようという
C ほとんど生活の一部となっているものが
D 危険にさらされている
E あらためて強く意識されるのは
例題:
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E
「~する時か~する時である」という2つの並列した構造を基本に作ると良い。[5]は「時」に接続する部分を選ばなければならないので、BかD。ただ、B→Dの流れが作れる。一方主語はEの部分である。ただし、先頭の文の直後にはEは合わないので、最初にCをいれると良い。したがって、正しい順番は、CEABDである。
彼は計画を立てるのが得意だ
例題:
A. この機械は使用するのが複雑だ
B. 私は早起きするのが苦手だ
C. 彼女は約束を守るのが一貫している
D. その店は値段が高い
E. この問題は解決するのが時間がかかる
「~するのが~だ」は能力や特性を表す用法ですが、この文脈では「得意」という特性に対して、「複雑」という特性が言及されています。したがって、Aが最適な選択肢です。Bは「苦手」という逆の特性を示しており、C、D、Eは文脈に合っていない表現です。
彼はスポーツをするのが楽しい
例題:
A. この本は有名だ
B. 彼女は絵を描くのが得意だ
C. 今日の会議は重要だ
D. 私は旅行が好きだ
E. その映画は感動的だ
この文では、「~するのが~だ」という表現は、特定の行動や趣味を表現しています。他の選択肢は文脈に合っていません。
彼女はコミュニケーションをとるのがうまい
例題:
A. この問題は難しい
B. 彼は音楽を楽しむ
C. 今日の天気は晴れだ
D. 私は読書が好きだ
E. その映画は面白かった
この文では、「~するのが~だ」という表現は、特定の行動や能力を表現しています。他の選択肢は文脈に合っていません。
彼は人々を励ますのが上手だ
例題:
A. その本は面白い
B. 彼女は音楽が好きだ
C. 今日の仕事は忙しい
D. 私は料理が得意だ
E. この映画は感動的だ
この文では、「~するのが~だ」という表現は、特定の行動や能力を表現しています。他の選択肢は文脈に合っていません。
彼はチームで協力するのが重要だと言った
例題:
A. この問題は難しい
B. 彼女は言葉が上手だ
C. 今日の天気は晴れだ
D. 私は読書が好きだ
E. その映画は興奮させる
この文では、「~するのが~だ」という表現は、特定の行為や行動の重要性を表現しています。他の選択肢は文脈に合っていません。
彼は料理を作るのが上手だ
例題:
A. この本は有名だ
B. 彼女はスポーツが得意だ
C. 今日の会議は重要だ
D. その映画は感動的だ
E. 私は音楽を楽しむ
この文では、「~するのが~だ」は特定の行為に対する特性や能力を表現しています。他の選択肢は文脈に合っていません。
彼はプログラミングを学ぶのが努力家だ
例題:
A. この映画は感動的だ
B. 彼女は絵を描くのが得意だ
C. その店は高級だ
D. 私は旅行が楽しい
E. 今日の仕事は忙しい
この文では、「~するのが~だ」は特定の行為に対する特性や能力を表現しています。他の選択肢は文脈に合っていません。
この子供は数学を学ぶのが楽しい
例題:
A. 彼は料理が上手だ
B. その本は有名だ
C. 彼女は音楽が好きだ
D. 今日の天気は悪い
E. 私は旅行が好き
この文では、「~するのが~だ」は特定の行為に対する楽しみや好みを表現しています。他の選択肢は文脈に合っていません。
彼は新しい言語を学ぶのが速い
例題:
A. この料理は美味しい
B. 彼女はスポーツが得意だ
C. 今日の会議は重要だ
D. その映画は面白かった
E. 私は音楽を楽しむ
この文では、「~するのが~だ」は特定の行為に対する能力を表現しています。他の選択肢は文脈に合っていません。
彼女は詩を書くのが情熱だ
例題:
A. 彼は絵を描くのが趣味だ
B. その映画は感動的だった
C. この本は面白い内容だ
D. 私は音楽を聴くのが好きだ
E. 今日の天気は良い
この文では、「~するのが~だ」は特定の行為に対する情熱や趣味を表現しています。他の選択肢は文脈に合っていません。
急に起きる変動・大事件。 また、突然うけた衝撃
例題:
A. 青天の霹靂
B. 隣の芝生は青く見える
C. 青は藍より出でて藍より青し
D. 青菜に塩
E. 出藍の誉れ
用例:彼の人事の話は、まさに青天の霹靂だった。
隣の芝生は青く見える→他人が持っているものがやたらと良く見えてしまうこと
青は藍より出でて藍より青し→教えを受けた人が教えた人より優れること
青菜に塩→すっかり生気をなくして、ぐったりしているさま
出藍の誉れ→弟子が師匠の学識や技量を越えること
恵みの雨
例題:
A. 五月雨
B. 時雨
C. 慈雨
D. 氷雨
E. 霙(みぞれ)
用例:難民にとって国連の救援物資は干天の慈雨だった
五月雨→旧暦5月ごろに降る長雨
時雨→秋の末から冬の初めごろに、降ったりやんだりする小雨
氷雨→雹(ひょう)や霰(あられ)のこと
霙→雨と雪が混ざって降る気象現象
その人の根本の心構え。心の持ち方
例題:
A. 品性
B. 気性
C. 持ち前
D. 性根
E. キャラクター
用例:彼は性根が正直だ。
品性→人格や性格など、人の内面にある品
気性→生まれつきの気質・性格のこと
持ち前→その身にもともと備わっているもの
キャラクター→性格。人格。その人の持ち味
勢いよく進むさま
例題:
A. 風を切る
B. 切りを付ける
C. 口火を切る
D. 啖呵を切る
E. 見得を切る
用例:風を切るように、颯爽と歩き去る。
切りを付ける→一段落させること
口火を切る→人々の先頭を切って物事を始めること
啖呵を切る→歯切れのよい言葉でまくし立てること
見得を切る→大げさな言動をとって、自分の自信のほどを強調すること
特定の人物をひいきすること。力を貸すこと
例題:
A. 肩入れする
B. 助け舟を出す
C. 後ろ盾となる
D. 追い風が吹く
E. 一肌脱ぐ
用例:弱い立場の人に肩入れする
助け舟を出す→人が困っているときに力を貸して助けること
後ろ盾となる→かげにいて助けること
追い風が吹く→状況が有利に進展していること
一肌脱ぐ→誰かのために労力を惜しまずに手助けをすること
かざりけがなく正直なこと
例題:
A. 単刀直入
B. 愚直
C. ひたむき
D. 実直
E. 率直
用例:自分が思っていることを率直に言う
単刀直入→前置きなしにいきなり本題に入ること
愚直→知恵がなく正直一途で、臨機応変の才がないこと
ひたむき→一つの物事だけに心を向けているさま
実直→誠実でかげひなたのないこと
完全に緊張感がなくなり、思考停止の状態になること
例題:
A. 魔が差す
B. 緊張が解ける
C. 緊張の糸が切れる
D. ぬるま湯につかる
E. うかうかする
用例:あまりのプレッシャーで緊張の糸が切れてしまった。
魔が差す→思いもよらない出来心を起こす
緊張が解ける→不安に感じていた物事が解決すること
ぬるま湯につかる→安楽な現状に甘んじて、呑気に過ごす
うかうかする→不注意でぼんやりしているさま
両頬をぷくっとふくらませた、不平そうな顔つき
例題:
A. 浮かない顔
B. 膨れっ面
C. しかめっ面
D. 素知らぬ顔
E. 不承顔
用例:親の注意で、その子は膨れっ面をした
浮かない顔→心配事などがあって、晴れ晴れしない顔つき
しかめっ面→不快そうな顔つき
素知らぬ顔→知っていながら、知らないふりをする顔つき
不承顔→気が進まない顔つき
主に主食を指す、エネルギー源としての資源的な食べ物
例題:
A. 食品
B. 食料
C. 食材
D. 食事
E. 食糧
用例:今年は食糧不足が問題になった。
食品→人間が日常的に食物として摂取するものの総称
食料→食物の原材料。食用にするもの。
食材→料理を作るための、素材となる食べ物
食事→日々習慣的に何かを食べること
同じ思想や考え方によって築かれた友
例題:
A. 知己
B. 友人
C. 水魚の交わり
D. 同志
E. 竹馬の友
用例:同志の助けを得て乗り越える
知己→自分をよく理解してくれる友人や親友
友人→いつも親しくつきあっている人
水魚の交わり→たいへんに親密な友との関係
竹馬の友→幼友達
進行していた計画や物事が途中で行き詰り、だめになること
例題:
A. 頓挫
B. 失敗
C. 逆効果
D. 徒労
E. 粗相
用例:会社の計画が頓挫してしまった。
失敗→うまくいかなくなること
逆効果→行ったことが狙ったことと逆の結果に終わってしまうこと
徒労→やってきた苦労が無駄に終わること
粗相→不注意や軽率さから過ちを犯すこと
猫:( )
例題:
A. チワワ
B. プードル
C. マルチーズ
D. アメリカンショートヘア
E. レトリバー
ダックスフンドは犬の一種。同様にアメリカンショートヘアは猫の一種。
ドイツ:( )
例題:
A. プッチーニ
B. チャイコフスキー
C. ヘンデル
D. ベートーヴェン
E. ドビュッシー
モーツァルトはオーストリア出身の作曲家。同様にベートーヴェンはドイツ出身の作曲家。
17世紀:( )
例題:
A. 関ヶ原の戦い
B. 本能寺の変
C. 承久の乱
D. 戊辰戦争
E. 天草・島原の乱
応仁の乱は15世紀の出来事のひとつ。同様に天草・島原の乱は17世紀の出来事のひとつ。
バルト三国:( )
例題:
A. アルメニア
B. エストニア
C. エリトリア
D. アルバニア
E. ルーマニア
オランダはベネルクス三国に属する国。同様にエストニアはバルト三国に属する国。
平行四辺形:( )
例題:
A. 台形
B. 直方体
C. 立方体
D. ひし形
E. 正六角形
正三角形は二等辺三角形の一分類。同様にひし形も平行四辺形の一分類。
家:( )
例題:
A. 鍵
B. サイレン
C. カーテン
D. センサー
E. インターホン
セキュリティソフトはコンピュータを守る役目。同様に鍵は家を守る役目。
日差し:( )
例題:
A. サンダル
B. ビーチボール
C. クーラーバッグ
D. サングラス
E. ハット
傘は雨を防ぐ役目。同様にサングラスは日差しを防ぐ役目。
ソフトクリーム:( )
例題:
A. スプーン
B. コーン
C. ナフキン
D. フォーク
E. カフェテリア
カップは飲み物を飲む役目。同様にコーンはソフトクリームを食べやすくする役目。
プログラミング:( )
例題:
A. コーディングスキル
B. デバッガ
C. コンパイラ
D. アルゴリズム
E. プログラミング言語
コンピュータにはハードウェアが必要。同様にプログラミングにはプログラミング言語が必要。
映画:( )
例題:
A. カメラ
B. チケット
C. ポップコーン
D. 予約
E. 上映時間
航空券は旅行の役目。同様にチケットは映画を見るための役目。